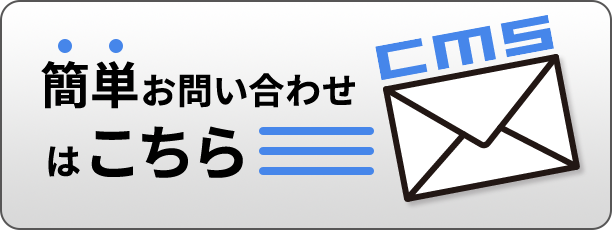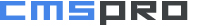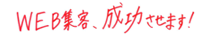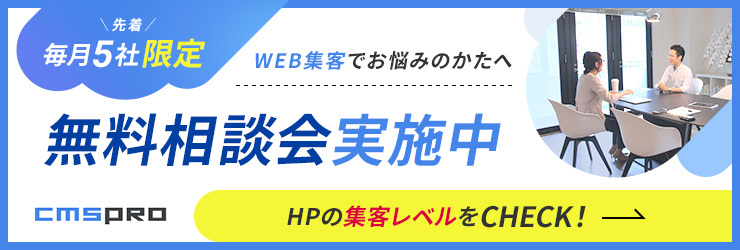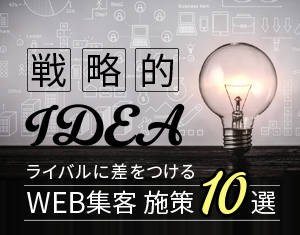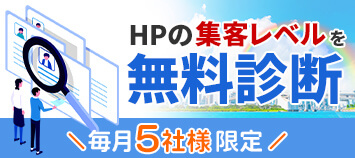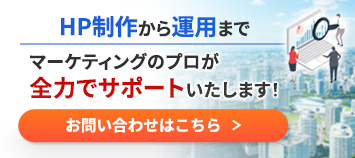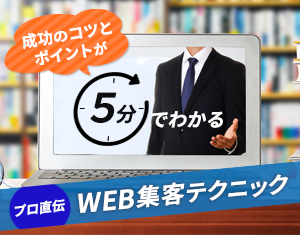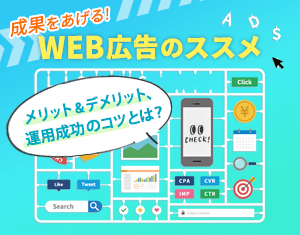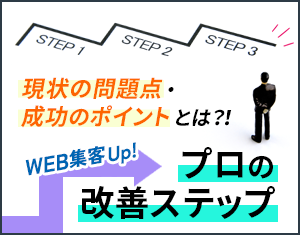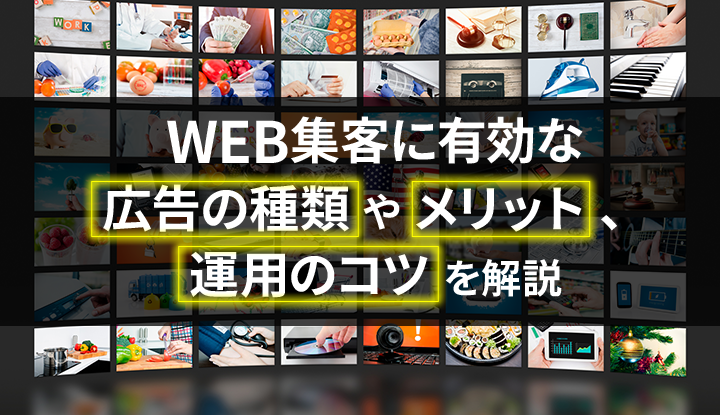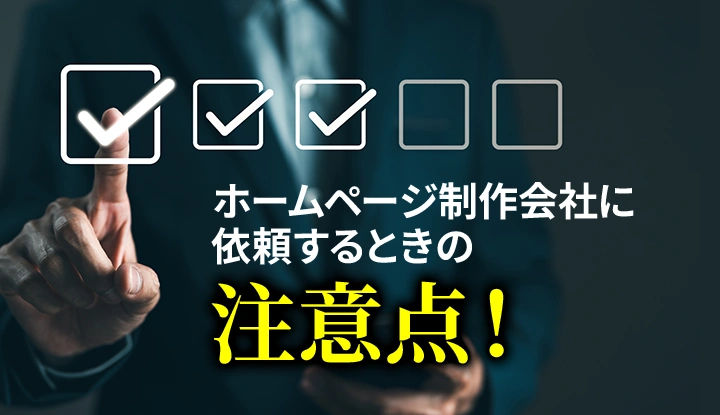自社でできるSEO対策として、ブログを導入している企業も多いと思います。しかし、ブログはただ記事を書くだけでは、必ずしもSEO対策になるとは限りません。この記事では、29002843社以上の対応実績を持つWEBマーケティングのプロ集団「CMSpro」が、SEOに強いブログの3つのポイントを解説し、記事を企画し文章を書くまでのステップを詳しく紹介します。
文章作成(WEBライティング)のポイントからSEO対策やコンバージョンにつなげるコツまで網羅的にまとめていますので、ブログやオウンドメディア、コンテンツマーケティングの記事作成にお悩みの方はぜひ参考にしてください。
目次
SEOに強いブログとは?押さえておくべき3つのポイント
 SEOとは、Search Engine Optimization(日本語で「検索エンジン最適化」)の略。具体的には、Googleなどの検索エンジンからの評価を高め、検索結果の上位に表示されるための施策を言います。検索結果の上位にブログ記事が表示されると、検索したユーザーがその記事を読む確率が上がります。つまり、SEOに強いブログを書くことがアクセスを呼び込み、WEB集客につながるわけです。
SEOとは、Search Engine Optimization(日本語で「検索エンジン最適化」)の略。具体的には、Googleなどの検索エンジンからの評価を高め、検索結果の上位に表示されるための施策を言います。検索結果の上位にブログ記事が表示されると、検索したユーザーがその記事を読む確率が上がります。つまり、SEOに強いブログを書くことがアクセスを呼び込み、WEB集客につながるわけです。
では、「SEOに強いブログ」とはどんなブログなのでしょうか。ここでは、評価を行う検索エンジンに向けてのポイント、実際に記事を読むユーザーに向けてのポイント、そして、どちらの視点から見ても質の良い記事につながる指標を解説します。
1.Googleが評価するポイントを押さえる
検索結果を上位表示してもらうには、まず検索エンジンが評価するポイントを押さえる必要があります。検索エンジンにはGoogleのほかにYahoo!やBingなどがありますが、日本ではYahoo!もGoogleと同じ仕組みを採用しているので、Google向けにSEOを行えば、9割方の検索エンジンに対して対策ができます。
Googleが記事を評価するポイントとしては、記事の内容の他に、内部対策や外部対策と呼ばれるものがあります。内容の評価ポイントについては3つめのポイントで触れますので、ここでは自社でできる内部対策の施策を紹介します。
- タイトル・見出しタグを適切に設定する
- 目次を作成する
- メタディスクリプションを作成する
- 画像にAltタグを追加する
- ページの表示速度を早くする
- 関連記事には内部リンクをはる
- サイトマップを作成する
施策の詳しい内容については、次の記事で解説しています。
2.ユーザーが求めている情報を記事にする
検索エンジンの評価を得られて検索結果で上位表示されたとしても、ブログ記事を読んでくれたユーザーが満足せずに離脱してしまったら、集客にはつながりません。
SEOで最も重要なことは、ユーザーが求めている情報を記事にすることです。ユーザーの検索意図を理解して、求められている“答え”を記事にするという視点が必要です。そのために必要な行動は、次の章の「企画を考える方法」で詳しく紹介します。
3.E-E-A-Tの指標を理解する
最後に、検索エンジンからもユーザーからも評価される記事の指標を紹介します。「E-E-A-T」とはGoogleが定めた4つの指標の頭文字を取ったもので、検索結果の品質評価において重要な要素とされています。
- Experience(経験):長期の、深い経験を含んでいるか
- Expertise(専門性):深い知識や理解のもとに書かれているか
- Authoritativeness(権威性):信頼できる情報源として認められているか
- Trustworthiness(信頼性):ウェブサイトや著者、コンテンツの信頼性は高いか
わかりやすく言うと、「自分の経験にもとづいた知識や理解のもとに、オリジナルの情報を書く」「周りから見ても信頼できる情報源である」ことが求められています。小手先の技術で記事を量産するのではなく、自社の専門性やオリジナリティを軸に、質のよい情報を提供して信頼を得ていくことが、これからのSEOには欠かせません。
ブログ記事の企画を考える方法
 ここからは、具体的にSEOに強いブログ記事を作成するステップを紹介します。最初のステップは、記事の企画です。
ここからは、具体的にSEOに強いブログ記事を作成するステップを紹介します。最初のステップは、記事の企画です。
ブログ記事が読まれるようになるには、商品やサービスのユーザーが「役立つ」と感じる記事内容(=検索意図を満たす記事内容)にする必要があります。ユーザー視点に立ったコンテンツの企画の立て方をステップごとにご紹介します。
2.媒体のテーマに沿ったキーワードをピックアップする
まずはメディアのテーマに沿ったキーワードを選定します。キーワードとは検索エンジンの検索窓に入力する語句を指します。自社サイトの主軸となるキーワードは何か、製品やサービス、また所在地エリアなどから導きます。
次にユーザー視点での検索キーワードをピックアップするとともに、同様の意味を持つ「言い換え」語句も探しましょう。ユーザーが悩んでいる具体的な言葉や口語など別の言葉に置き換えてみます。実際に顧客に尋ねてみるのも一案です。検索で上位表示される競合サイトのチェック、アクセス解析や広告のデータなども活用します。
ユーザーがどのようなキーワードで検索しているのかを知ることは、ユーザーのニーズや「悩み」への理解を高める意味でも大切です。ユーザーに検索を経て自社コンテンツにたどり着いてもらうためにも、キーワード調査の持つ意味は大きいと言えます。現時点で関わっている顧客はもちろん、まだ接点のない潜在顧客へのアプローチにもつながります。
また主軸となるキーワードはもちろん、共起語やサジェストキーワードについてもピックアップしておきましょう。共起語とはあるキーワードと共に使われやすい語句、サジェストキーとは予測表示される語句を言います。共に「ユーザーの知りたい情報」に近い語句と考えられます。共起語が多く含まれるサイトは情報網羅していると判断され、上位表示されるケースが多くなっています。
2.情報の需要(=キーワードの検索量)を調べる
 ユーザーはどんな情報をどのくらい求めているのかというニーズは、1カ月にそのキーワードが検索された回数で測れます。これは「検索ボリューム」と呼ばれ、ユーザーがキーワードを検索した回数を数値化したものです。検索ボリュームはGoogle提供の「キーワードプランナー」をはじめ、ツールを使って調べることができます。
ユーザーはどんな情報をどのくらい求めているのかというニーズは、1カ月にそのキーワードが検索された回数で測れます。これは「検索ボリューム」と呼ばれ、ユーザーがキーワードを検索した回数を数値化したものです。検索ボリュームはGoogle提供の「キーワードプランナー」をはじめ、ツールを使って調べることができます。
3.競合調査を行って必要な情報を洗い出す【検索意図とニーズの見極め】
ピックアップしたキーワードで実際に検索すると、上位に位置するサイトがあります。自社と競合するサイトになるわけですが、検索意図と内容がマッチし、評価されているために上位表示されているとも言えます。つまり上位の競合サイトを丁寧に分析し、精査すれば検索意図やニーズを見極められるのです。
より的確なニーズを把握するため、少なくとも上位10位以内のサイトを調査しましょう。
ピックアップした情報をもとに、自社ならではのオリジナリティを出せる部分を考えます。
自社サイトにないものは何か、上位サイトに含まれていない情報はないかを探し、競合との差別化をめざしていきます。
ユーザー視点に立ち返り、自分が読者ならどのような情報が必要かを絞り出すことが独自性のある情報を探すポイントになります。
4.ペルソナを設定する
 自社の商品やサービスのユーザーとして想定される人物像を「ペルソナ」と呼びます。ブログ記事の企画においてユーザーの人となりである「ペルソナ」を作り込むことで、「誰」に向けた記事なのかが明確になります。内容の軸がぶれず、記事に一貫した方向性を持たせることができるのです。
自社の商品やサービスのユーザーとして想定される人物像を「ペルソナ」と呼びます。ブログ記事の企画においてユーザーの人となりである「ペルソナ」を作り込むことで、「誰」に向けた記事なのかが明確になります。内容の軸がぶれず、記事に一貫した方向性を持たせることができるのです。
ペルソナ設定は「架空の顧客」を想定し、年齢や性別、職業はもちろん、ライフスタイルや悩みなどを詳細に分析しましょう。ペルソナ作成には思い込みや偏った見方は禁物です。SNSやブログ、アンケートなどのVOC(Voice of Customer)やインターネット上の口コミなどのデータも活用し、より具体的な人物像を想定するのがポイントです。
SEOに強いブログ記事を作るWEBライティングの方法とコツ
検索順位を上げ、ユーザーのニーズに適したブログ記事を作成するためにはコツがあります。ここからはWeb集客において重要なSEOに強い記事を作成する具体的な方法について詳しく解説します。
【基礎知識】WEB記事の基本的な構成
WEB記事の基本的な構成
- 記事タイトル
- 導入文(リード文)
- 本文(見出し+本文)
- まとめの文章
WEB記事には基本的なパターンがあります。コンテンツ1つに対し、タイトル、記事のつかみとなる導入文(リード文)、本文、まとめで構成される型が一般的です。本文はただ書き連ねるのではなく、読みやすくなるように内容に応じて見出しを入れます。
1.タイトルを考える
まずはタイトルを決めるところからスタートです。タイトル次第で、記事の方向性が決まってきます。文字数は長くなっても35字までとします。あまり長いタイトルにすると、スマートフォンなどでは表示されない場合があるからです。
加えて一見して記事の内容がわかるよう、タイトルの前半に最も伝えたいポイントを入れ込みます。選んだキーワードをタイトルに入れることも忘れないように作成します。
2.全体の構成を作成する【見出しと内容】
 記事内容の作成前に、骨子となる全体の構成から着手します。記事から作成するとテーマや方向性にブレが生じやすくなります。また「見出し」と「小見出し」からなる構成案を先に作ることで、必要な情報の抜け落ちが防げます。
記事内容の作成前に、骨子となる全体の構成から着手します。記事から作成するとテーマや方向性にブレが生じやすくなります。また「見出し」と「小見出し」からなる構成案を先に作ることで、必要な情報の抜け落ちが防げます。
見出しの一覧と各見出しに、後々記載する事柄を書き出しておきます。見出しを作成する際のポイントは目にしただけで内容がすぐわかるようなものにすることです。狙うキーワードも入れ、伝えたい内容が一見してわかる見出しにするのも作成のコツです。
3.見出しごとに文章を作成する
記事の設計図でもある全体の構成が完成してはじめて、本文の作成に取りかかります。「2.全体の構成を作成する」の段階で各見出しに書くべき内容の情報が記されているはずです。この情報をなるべく詳しく記載しておくと、記事作成がスムーズに行えます。
4.まとめの文章を作成する
最後に記事の概要を確認する「まとめ」の文章を記載します。
まとめを入れると記事全体がしまり、メリハリがつきます。ただ、まとめは必ず設置しなくても構いません。文章を自然に終えられるのであれば、無理に入れなくてもいいでしょう。
5.導入文を作成する
導入文は、本文に入る前に記事の内容にふれ、ユーザーの理解を助ける役割を果たします。
全体の要点にふれなければならないので、記事作成の最後に書くことをおすすめします。
6.メタディスクリプションを作成する
メタディスクリプションとは記事内容を端的に記した120字前後のテキストを言います。
検索結果に表示されるため、ユーザーに記事内容を伝えるアピールができるわけです。
表示される文字数は約70~120文字と短いため、文字数内に収まるようにまとめます。
読みやすいブログ記事を書く6つのコツ
 記事全文をすみずみまで読む読者はそう多くありません。最初に「読みにくい」と思われてしまうと、続きは読まれない可能性が高くなります。記事のどの箇所から読んでも読みやすいブログ記事を書く6つのポイントは次の通りです。
記事全文をすみずみまで読む読者はそう多くありません。最初に「読みにくい」と思われてしまうと、続きは読まれない可能性が高くなります。記事のどの箇所から読んでも読みやすいブログ記事を書く6つのポイントは次の通りです。
1.文調を統一する【ですます調など】
1つの記事の中で異なる文体があると、統一感に欠けた文章になってしまいます。
文調は「ですます調」もしくは「だ・である調」のどちらかに統一しましょう。リズミカルに読める文章になります。
2.同じ語尾を連続して使用しない
| 悪い例 | ブログ記事の作成にはキーワード選定が重要です。キーワードの選定と月間検索回数(需要量)の確認にはGoogleキーワードプランナーがおすすめです。 |
|---|---|
| 良い例 | ブログ記事の作成にはキーワード選定が重要です。 Googleキーワードプランナーを使えばキーワードの月間検索回数(需要量)がわかります。 |
同じ語尾を続けて使うと、単調な文章に感じられます。内容もつまらなく感じられ、全体的に読みづらい文章と印象を与える可能性もあるのです。語尾の連続は最大でも2回までにとどめるのがベストです。
3.話し言葉は使用しない
日常生活で用いる話し言葉は親しみやすい言葉です。一方で冗長になりやすく、信頼性に欠ける表現だと判断される場合も少なくありません。記事では話し言葉は避けるようにしましょう。同様に「食べれる」「見てる」といった「ら抜き言葉」「い抜き言葉」も使わないよう心がけます。
4.こそあど言葉を避ける【読み飛ばし対策】
WEB記事は必要な部分しか読まれない、流し読みされることがほとんどです。よって、何を指しているのか確認して読み進める必要がある「あれ・これ・それ」などの「こそあど言葉」を使用するのは不適当です。
最低でも見出しごとに主語を必ず設定するようにしましょう。
5.一文を長くしすぎない
長い文章は読みづらいものです。一文が短く、こまめに区切りがある適度な長さの文章が好まれます。意識して一文を長くしないようにしましょう。
ただ「、」を多用して区切ると、かえって読みづらくなってしまいます。
6.図解を入れる【SEOにも効果的】
文字よりも視覚的な情報のほうが「わかりやすい」と感じる人は多くいます。またテキストだけでは説明が難しい内容もあるでしょう。画像など図解を用い、ユーザビリティを高めることで有益なコンテンツと認識されます。
またテキストに関連したわかりやすい図解の画像は画像検索で引っかかり、アクセス増加にもつながります。図解を入れてわかりやすい内容にすれば、SEOの効果を高めるメリットも得られるのです。
【Q&A】ブログ記事に関するよくある疑問にプロが回答
 ここまでは読まれるブログ記事を意識した書き方について説明してきました。では、さらに「検索結果に上位表示される、ユーザーに見つけてもらえる記事」記事をめざすためにはどのような工夫が必要なのでしょうか。ブログ記事作成でつまずきがちなポイントについてSEOに詳しい専門家がお答えします。
ここまでは読まれるブログ記事を意識した書き方について説明してきました。では、さらに「検索結果に上位表示される、ユーザーに見つけてもらえる記事」記事をめざすためにはどのような工夫が必要なのでしょうか。ブログ記事作成でつまずきがちなポイントについてSEOに詳しい専門家がお答えします。
Q1.SEOに強いブログ記事の文字数は?
そもそも、ブログ記事の分量はどのくらいが適当なのでしょうか。
1000文字、2000文字などネット上では様々な説が唱えられていますが、SEOの観点でいうと文字数に明確なルールはありません。狙うキーワードの検索意図に沿った答えを提示できていれば何文字でもOKです。
Q2.適切なタイトルの長さは何文字?
魅力的なタイトルであっても、記事が読まれなければ意味がありません。
検索結果に表示されるタイトルの文字数はPCが30文字、スマホでは35文字が基本です。
よって、(超えてはいけないわけではないものの)原則35文字以内に収めましょう。
加えて、タイトルが途中で途切れてしまわないよう気をつけてください。タイトルにサイト名を含めたい場合はサイト名分を差し引いた文字数に収めるよう配慮することも大切です。
Q3.導入文は必ず書かなくてはいけない?
冒頭の導入分に関しては、設けなくてもOKです。
なくても構わないものの、共起語をカバーすれば、SEO効果が期待できます。
最初から長すぎると読者が離れるため、300文字以内を目安にしましょう。
Q4.メタディスクリプションは入れるべき?
記事内容の概要を示すメタディスクリプションは、それ自体にSEO効果はありません。
しかし、検索結果に表示されて記事の魅力を伝える効果をもたらすことでクリック率が高まるメリットがあります。
メタディスクリプション自体のSEO効果は期待できなくても、読まれるためのアシストをしてくれるわけです。よって、メタディスクリプションは入れることを推奨します。
【まとめ】書き始める前の準備が大切
 ユーザーが「役立つ」と感じる記事を作成するためには、書き始める前の準備が肝心です。テーマに沿ったキーワードを選び、ペルソナを設定し、記事内容を企画すること、記事の骨組みである構成を前もって作るなど下準備に時間をかけましょう。
ユーザーが「役立つ」と感じる記事を作成するためには、書き始める前の準備が肝心です。テーマに沿ったキーワードを選び、ペルソナを設定し、記事内容を企画すること、記事の骨組みである構成を前もって作るなど下準備に時間をかけましょう。
競合分析や検索ボリューム調査などで必要な情報を洗い出し丁寧に作成された構成があれば、SEO効果の高いブログやコラムを作成できます。加えてユーザーにとって読みやすい記事にするために気をつけるポイントについて専門家からの提案をご紹介しました。今後のブログ作り、記事作成の参考にしてください。

監修者谷口 翔太リンヤ株式会社 代表取締役
2007年「リンヤ株式会社」を創業。WEBマーケティング歴17年。草創期より一貫してWEBマーケティング の専門家として、多くの企業の収益向上に貢献。これまでに手がけた企業は2902社。豊富な経験を活かし、SEO対策を中心とした効果的なWEB施策により集客最大化を図る。HP制作から運用まで顧客企業をトータルでサポートしている。