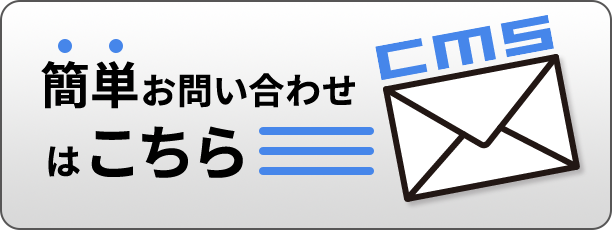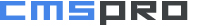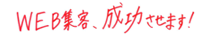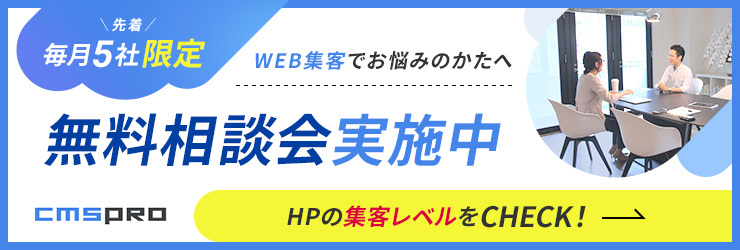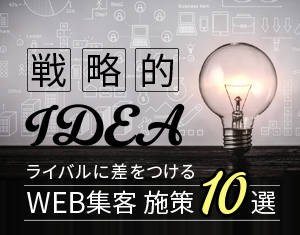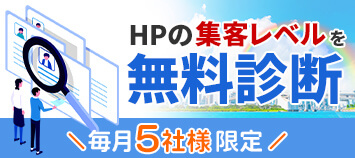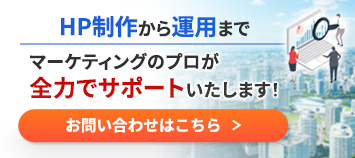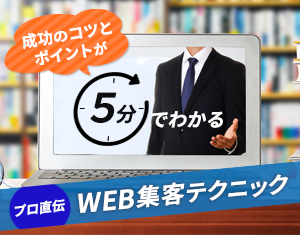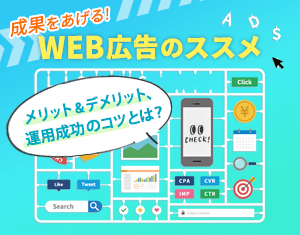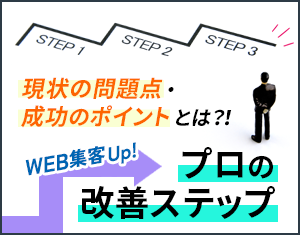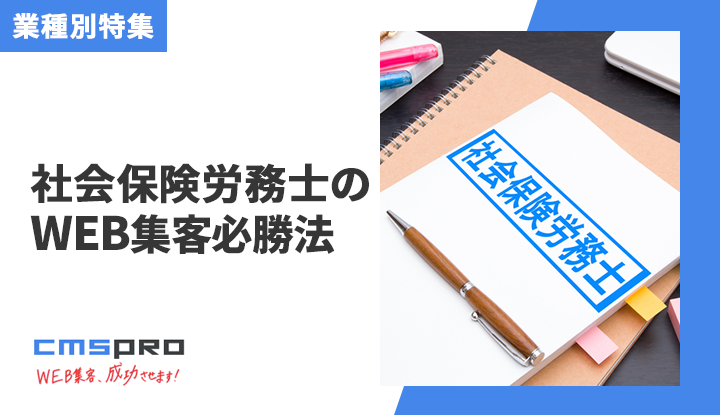
従来、社労士を探す場合には紹介や口コミといった方法を使って見つけていました。しかしインターネットを使って情報収集をすることが一般化したことにより、最近ではWebを使って探す人も増えています。今やWebによる集客は新規顧客獲得のチャンスなわけです。
しかしWeb集客には対策方法もあります。やみくもにホームページを立ち上げたとしても「問い合わせゼロ」という結果に終わってしまうかもしれません。
そこで本コラムでは、社労士に適したWEB集客方法をご紹介します。
この記事の伝えたいこと
- 社労士と相性の良いWeb集客方法には、「SEO対策」「リスティング広告」「SNS運用」があります。
- SEO対策では、検索したキーワードに地域名や業務内容を組み合わせた言葉で検索上位を目指すことが、社労士のWeb集客に効果的です。
- リスティング広告は、ユーザーが検索したキーワードに基づいて広告が表示されるため、社労士のサービスを求めている顕在層ユーザーへのアプローチに優れています。
- 社労士のWeb集客は何を行うにしても、ターゲットを明確化することが重要です
目次
なぜ社労士でWeb集客?
 社労士はWeb集客に向いているかどうか分からないと思うかもしれません。社労士は人事・労務管理や社会保険の手続き、労働紛争の解決などを専門に行う仕事のため、アナログ的な職業だと思われているからです。
社労士はWeb集客に向いているかどうか分からないと思うかもしれません。社労士は人事・労務管理や社会保険の手続き、労働紛争の解決などを専門に行う仕事のため、アナログ的な職業だと思われているからです。
しかし近年、増加による競争が激化しているのと同時に、コンプライアンス意識の高まりによる社労士の需要は増加してきています。Webによる情報収集が一般化してきている今こそ、このチャンスを捉えるために社労士によるWeb集客が求められています。
社労士と相性の良いWeb集客方法3選
 Web集客方法はいくつもありますが、ここからは社労士と相性の良いWeb集客方法である「SEO対策」「リスティング広告」「SNS運用」といった3つの方法をご紹介します。
Web集客方法はいくつもありますが、ここからは社労士と相性の良いWeb集客方法である「SEO対策」「リスティング広告」「SNS運用」といった3つの方法をご紹介します。
社労士と相性の良いWeb集客方法3選
SEOとは検索エンジン最適化のことであり、Search Engine Optimizationを略した言葉を言います。
そこでSEO対策とはGoogleなどの検索エンジンなどで、自身のWebサイトを上位に表示させる方法のことです。たとえば「就業規則 作成」といったキーワードを入力しWeb上でユーザー検索したときは、その検索内容に合致したWebサイトが検索エンジンに表示されます。そこで自身の事務所のサイトが検索エンジンの上位に表示されるよう対策を行うのです。この対策をすることにより、検索した人が自然に事務所のサイトへ訪れるようになります。
SEO対策はお金をかけずに効果は長続きしますが、検索エンジンの上位に表示されるまでには時間がかかることもあります。
おすすめの理由
SEO対策では、検索したキーワードの地域名や業務内容を組み合わせた言葉で検索上位を目指していきます。検索エンジンで上位表示されることにより、そのWebサイトの信頼性が高まると同時に、下位表示のキーワードで表示されたWebサイトよりも多くのユーザーに見てもらえる可能性が高まるようになります。
このことにより、検索エンジンから、そのWebサイトへ自然流入することが増加し、見込み顧客の獲得につながることから、オススメのWeb集客方法となっています。
SEOのはじめかた
ホームページ内にブログを開設します。そのホームページに対しては、専門的な知識やノウハウを入れ込んだコラム記事をできるだけ多く作成して公開します。
ただ、コラム記事がいくら多くなったとしても、漫然と記事をアップしただけでは成果につながりません。たとえば「Web 集客 方法」といったキーワードで検索された場合には、「Web集客にはどのような方法があるのか?」「その方法にはどのような特徴があるのか?」を解説する記事を作る必要があります。1つの記事に対して1つのキーワードを設定して、キーワードに関する情報を盛り込むことで検索結果の上位に表示されるようになります。
リスティング広告
リスティング広告は、GoogleやYahoo!JAPANなどの検索エンジンで検索結果ページが表示されたとき、その上部や下部に表示される広告のことです。そして、その広告をクリックした人が自身のホームページに訪れると広告費が発生する仕組みとなっています。
このリスティング広告は、ユーザー自身が検索したキーワードに合わせて表示されます。広告を打てばすぐに集客を始められ数日のうちに上位表示されるのが特徴ですが、広告を止めると集客も止まってしまうため、長期的な集客には他のWEB集客方法と組み合わせることが効果的です。
おすすめの理由
リスティング広告は「就業規則 作成」や「労働契約書 作成」などの具体的なキーワードで検索しているユーザーに対して、即座に広告を表示することができます。このように、ユーザーが検索したキーワードに基づいて広告が表示されますので、潜在層ではなく顕在層ユーザーへのアプローチに優れていることがおすすめの理由です。
リスティング広告のはじめかた
たとえばGoogleであれば、まず「Google広告」の公式サイトにアクセスし、アカウントを作成します。そこでターゲットとなるキーワードを含めた広告文を作成し予算を設定するだけで広告を掲載できます。
1クリックあたり数十円~数百円程度と比較的安価な費用で運用できます。
SNS運用
SNS運用とは、InstagramやYouTube、X(旧Twitter)、Facebook、LINEなどのSNSを使って、自身のホームページを発信する方法のことを言います。たとえば、SNSに対して「就業規則の作成事例」や「労務相談のポイント」などを投稿することで、そのSNSのフォロワーと交流ができ信頼関係も築くことができます。
SNSは基本的に無料で始められることができ、情報も拡散しやすいのが特徴ですが、長く集客を続けていくためには工夫や時間が必要となっています。
おすすめの理由
メジャーなSNSはユーザー数が圧倒的に多く存在しています。たとえば、X(旧Twitter)であれば他のユーザーの投稿を引用できることから拡散性が非常に高く、投稿が多くの人から注目を集める「バズる」という現象が発生すれば自身のホームページの認知度が一気にアップします。
SNS運用のはじめかた
発信したいSNSのアカウントを作成し、自身のプロフィールを設定します。そのプロフィールには事務所の名称や事業内容、連絡先などを掲載します。そして、そのプロフィールを充実させた上で、ターゲットに役立つ投稿を充実させるようにしましょう。
自社で投稿を行う場合には無料ですので、基本的に費用はかかりません。
失敗しがちなWeb集客の例と対策
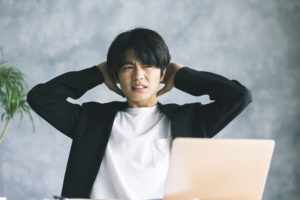 社労士のWeb集客は、費用をあまりかけずに実行でき新規顧客を獲得できる方法です。しかし無駄な費用がかかってしまったり、まったく新規顧客を獲得できなかったりして失敗することもあります。
社労士のWeb集客は、費用をあまりかけずに実行でき新規顧客を獲得できる方法です。しかし無駄な費用がかかってしまったり、まったく新規顧客を獲得できなかったりして失敗することもあります。
ここからは失敗しがちなWeb集客の例と対策を解説していきます。
誰に向けたサイトなのか分からない
社労士がWeb集客を始めても、サービス内容が広すぎて絞りきれていない場合には失敗しがちです。さらに個人事業主、中小企業、個人事業主、大企業、人事担当者など、ターゲットを明確に絞ることも大切です。
ターゲットが不明確であると、アクセスしてきたユーザーが「自分に関係ある話かどうか」の判断ができず、ホームページからすぐに離脱してしまいます。またそれでは、検索エンジンに対して専門性が伝わらないために検索結果で上位表示されず、SEO効果も低くなります。
広告の無駄打ちが多い
「100%経営者の味方」や「合法的に社会保険料を節約する方法はこちら」といった、過度に一方的なメリットを謳うリスティング広告は、不適切であるだけでなく、広告の無駄打ちにつながりやすいです。
こうした広告は、短絡的な利益のみを求める経営者や、社労士の業務内容を正しく理解していない層からのクリックを誘発します。しかし、労働者と経営者の公正な関係構築という社労士の本質的な価値を求めている見込み客には響きません。
結果として、クリックはされるものの、問い合わせや契約には結びつかないため、広告費ばかりがかさみ、費用対効果が極めて悪くなってしまうのです。
対策の鍵はズバリ「ターゲットの明確化」
Web集客を成功させるためには、「誰に、どのような価値を提供したいか」を明確にすることが不可欠です。
例えば、「労働時間はそのままに残業代を大幅削減」といった広告は、特定の経営者には魅力的に映るかもしれません。しかし、本当に困っている中小企業経営者は、単なるコスト削減ではなく、従業員との信頼関係を築きながら、健全な経営を目指したいと願っているはずです。
ターゲットを「労働環境の改善を通じて、従業員の定着率を上げたい経営者」のように明確にすることで、提供すべきコンテンツの内容や選定すべきキーワードが定まります。これにより、あなたの事務所の価値観に共感してくれる質の高い見込み客と出会えるようになり、結果的に無駄な広告費を削減し、高い費用対効果を実現できます。
顧客から選ばれやすい社労士のポイント
 社労士は人事部や総務部などにしか関わることがなく、法律に関わる小難しいことばかり話しているカタい専門職と思われているかもしれません。そう思われているのはイメージであり、Web集客で社労士が変わっていくことでそのイメージも変わり新規顧客も獲得できるようになります。
社労士は人事部や総務部などにしか関わることがなく、法律に関わる小難しいことばかり話しているカタい専門職と思われているかもしれません。そう思われているのはイメージであり、Web集客で社労士が変わっていくことでそのイメージも変わり新規顧客も獲得できるようになります。
そこでここからは、顧客から選ばれやすい社労士のポイントを解説します。
①難しい言葉を多用しすぎない
社労士には、社会保険や労働保険に関する一般的では専門用語も多くあります。このような専門用語を使わないと社労士の仕事内容は説明できないと思っているかもしれませんが、難しい専門用語はできるだけ避けて顧客が理解しやすい一般的な言葉で説明していくことが大事です。
そのためには、専門用語を平易で分かりやすい言葉に言い換えたり身近な具体例に置き換えたりすることが必要です。言葉だけでなく図を活用して、専門用語をわかりやすくすることも大事です。
②密にコミュニケーションをとっている
どんなに高い品質のサービスを提供したとしても顧客を不安にさせるのでは選ばれなくなります。顧客の話に耳を傾け、共感しながら対応するといった密なコミュニケーションをとることで、顧客と社労士の信頼関係構築につながり選ばれるようになります。
成功している社労士のWeb集客事例~伊藤事務所様
社会保険労務士伊藤事務所では、1年間ホームページを出していたものの問い合わせはほぼゼロでした。そこでCMSproがホームページを一新するのと同時にリスティング広告やSEO対策を実施した結果、コンスタントに毎月10件は新規問い合わせが届くようになり、そのうち毎月2~3件は受注できるようになりました。繁忙期には7~8件を受注できた月もあったのです。
CMSproでは、伊藤事務所から、さまざまなお話をお伺いし広告運用にフィードバックすることで、今後も毎月3件は受注することを目標にしています。
「問い合わせゼロ」から脱却する改善チェックリスト
社労士が「問い合わせゼロ」から脱却し新規顧客獲得するためには、以下の内容をチェックする必要があります。
表に記載している「チェック項目」を一気にすべて実行しようとせず、一回あたり3つずつ程度、見直すと良いでしょう。もし可能であれば、自身のホームページを知人やWeb制作者といった第三者に確認し評価してもらうのも良いかもしれません。
| 区分 | チェック項目 | 改善できるポイント |
|---|---|---|
| 集客の入口 | HPは検索で出てくるか? (「事務所名・地域+社労士」で検索) |
キーワードをタイトルや見出し・コラムに入れる。 |
| 専門分野が明確か? | 「誰に何を提供するか」が曖昧だと選ばれにくい。 特化して差別化させる。 |
|
| Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)を登録していない | 写真・営業時間・業務内容・口コミを充実させる。 | |
| SNSやブログの更新が止まっていないか? | 活動していない印象になる。最低月1回は投稿する。 | |
| 第一印象 | 事務所情報が不十分(住所、連絡先、営業時間など) | 実在性が伝わらず不安要素に。詳細な情報で信頼性をアップ。 |
| 実績や得意分野が見えない | 数字・事例・資格などで「何ができるか」を明確にする。 | |
| クライアントの声・事例紹介がない | 実績証明+信頼獲得の強力ツール。OKがもらえるなら掲載すべき。 | |
| 導線と動機 | 問い合わせフォームがわかりにくい/使いにくい | 「無料相談はこちら」などのボタンをわかりやすく配置。入力項目は最小限に。 |
| 電話番号やメールアドレスの掲載がない/目立たない | 今すぐ連絡したい人のために、目立つ場所に固定表示(ヘッダーやフッター)する。 | |
| CTA(行動喚起)がない/弱い | 「●●に悩んでいませんか?無料でご相談いただけます」など明確な誘導を入れる。 | |
| 無料相談や問い合わせのハードルが高い | 初回無料、Zoom対応、資料プレゼントなど、気軽さ・特典を提示する。 | |
| 問い合わせ後の流れが不明 | 「ご相談後の流れ」を図解で紹介すると安心感がアップする。 | |
| 継続 | アクセス解析をしていない(Googleアナリティクス等) | どこから来て、何を見て離脱しているのかを把握して改善につなげる。 |
| 問い合わせが来ない理由を聞いていない | 顧客や同業に「なぜ相談しようと思ったか/しなかったか」リサーチする。 | |
| 他の社労士と自分の違いを言語化できない | 競合サイトを見て、専門性やスタンスの差を明確にする。 |
社労士のWEB集客よくあるご質問
Q1: なぜ今、社労士にとってWeb集客が重要なのでしょうか?
A1: 現代では、多くの人が情報をWebで調べています。そのため、社労士もWeb上で情報を発信し、アプローチすることで、これまで接点のなかった潜在的な顧客にサービスを知ってもらい、集客に繋げることが不可欠だからです。
Q2: 社労士がWeb集客を始める際、どんな方法が効果的ですか?
A2: 主に「SEO対策」「リスティング広告」「SNS運用」の3つが効果的だと考えられます。これらは、社労士の業務内容やサービスを求める顧客層と相性が良く、それぞれ異なるアプローチで集客を促進できます。
Q3: Web集客で顧客と信頼関係を築くために、最も大切なことは何ですか?
A3: 顧客の話にじっくり耳を傾け、共感しながら丁寧に対応する「密なコミュニケーション」が最も大切です。Webを通じて接点を持った後も、このようなきめ細やかな対応を心がけることで、顧客は社労士に安心感を覚え、長期的な信頼関係へと繋がります。
まとめ
近年、増加による競争が激化しているのと同時に、コンプライアンス意識の高まりにより社労士の需要は増加しています。このチャンスを捉えるために、Webによる情報収集が一般化してきている今こそ、社労士によるWeb集客は必要です。
社労士と相性の良いWeb集客方法には、「SEO対策」や「リスティング広告」「SNS運用」がありますが、失敗しがちなWeb集客の仕方もありますので、失敗しがちな具体例とその対策をよく確認するようにしましょう。
Web集客を最大化したいと考えている社労士であれば、CMSproへお問い合わせ・お申し込みください。

監修者谷口 翔太リンヤ株式会社 代表取締役
2007年「リンヤ株式会社」を創業。WEBマーケティング歴17年。草創期より一貫してWEBマーケティング の専門家として、多くの企業の収益向上に貢献。これまでに手がけた企業は2902社。豊富な経験を活かし、SEO対策を中心とした効果的なWEB施策により集客最大化を図る。HP制作から運用まで顧客企業をトータルでサポートしている。